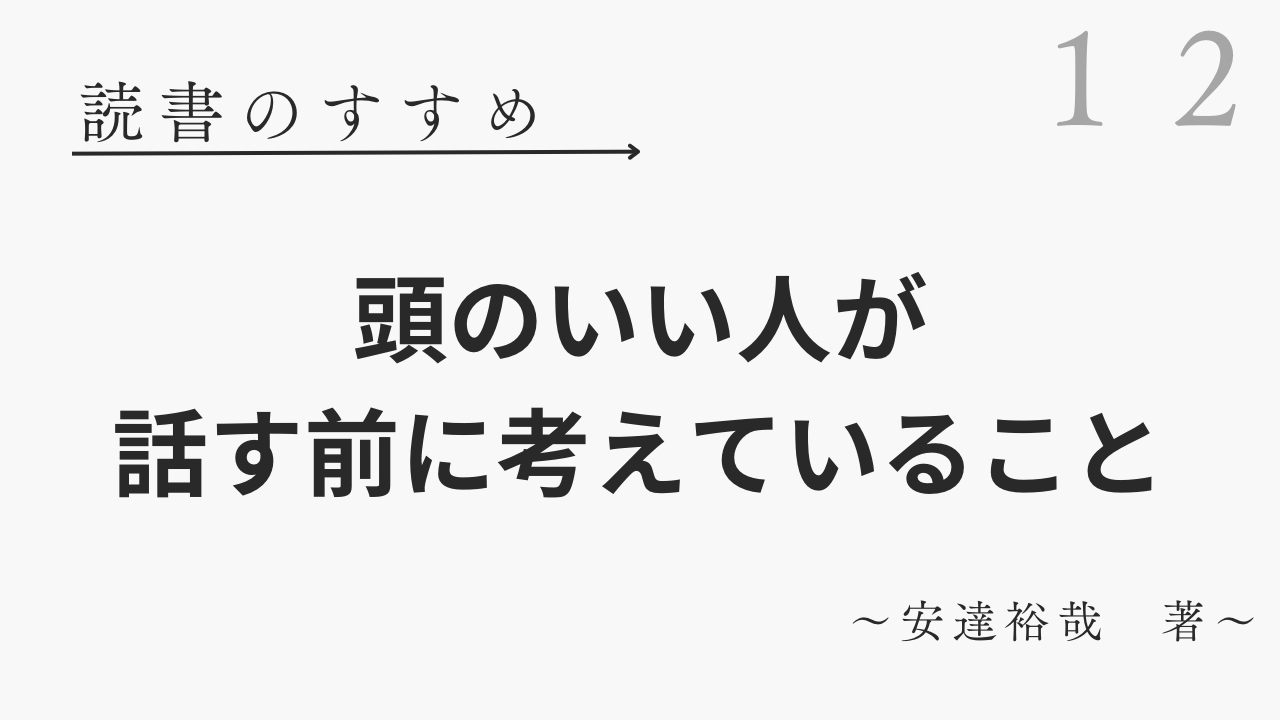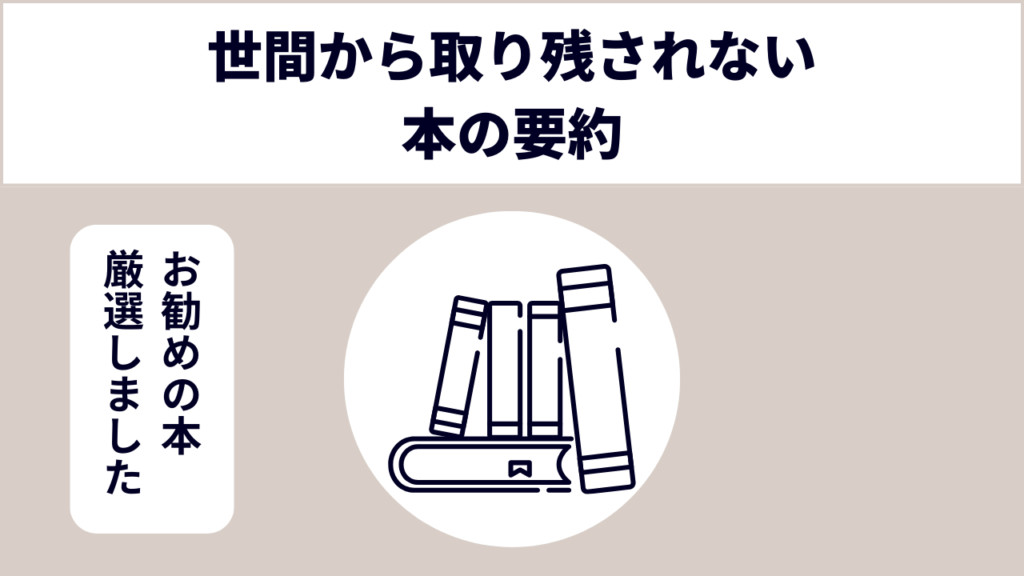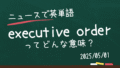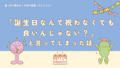「話すたびに自分の頭の悪さが露呈している気がする…」
「うまく話せる人と自分はなにが違うのだろう?」
そんな悩みを解決すべく、安達裕哉氏の著書「頭のいい人が話す前に考えていること」という本を読んでみました。
読んでみると、自分が普段仕事で感じていた悩みの解決の道が示されるとともに、周囲の人に感じていた掴めない感が晴れ、スッキリしました。
大雑把な要約と感想をまとめます。
要約
頭のいい人が話す前に考えていること
- とにかく反応するな
- 頭のよさは、他人が決める
- 人はちゃんと考えてくれてる人を信頼する
- 人と闘うな、課題と闘え
- 伝わらないのは、話し方ではなく考えが足りないせい
- 知識はだれかのために使って初めて知性となる
- 承認欲求を満たす側に回れ
1. とにかく反応するな
話す前にちゃんと考えることができる人は、キレません。
感情的にならず冷静に対応しましょう。
2. 頭のよさは、他人が決める
皆が自分の考えを優先する時代だからこそ、一旦相手の立場に立ち、頭のいい人になって考えてみましょう。
3. 人はちゃんと考えてくれてる人を信頼する
賢いふりをしないようにしましょう。
人の意見に後から意見する方が簡単ですが、会議では最初に発言するようにしましょう。
4. 人と闘うな、課題と闘え
論破するのはやめましょう。論理的に説得できても解決はしません。
5. 伝わらないのは、話し方ではなく考えが足りないせい
型に当てはめただけでは考えたことにはなりません。
6. 知識はだれかのために使って初めて知性となる
知識は披露せずに相手のために使いましょう。
7. 承認欲求を満たす側に回れ
みな承認欲求を満たしてもらいたいのです。満たす側に回りましょう。
頭のいい人になる思考の深め方
1. 客観的な情報を用いる
根拠のある話をしましょう。
言葉の定義を曖昧にしないようにしましょう。
2. 話を整理する
話す前に話す内容を整理することに時間を使いましょう。
結論から話すことで、相手の聞くスイッチを入れましょう。
「事実」と「意見」を分けましょう。
3. 傾聴する
他人が話しているときに、自分が話すことを考えず、相手は何を言いたいのかを考えながら聞きましょう。
安易に肯定や否定をしたり相手を評価したり意見を言ったりせず、相手の話を整理しましょう。
話が途切れても沈黙し、好奇心を総動員して相手の話を引き出しましょう。
4. 質問する
相手の話を深掘りする質問をしましょう(過去の行動、状況・行動・成果/結果の深掘り、仮定の状況における行動を聞く)。
質問の前に、相手の立場に立ったり反対意見の人の立場に立ったりし、仮説を立てましょう。
知りたいことを明確にし、聞くべき人(聞きやすい人ではなく詳しい人)に聞きましょう。
5. 言語化する
言語化する労力を誰が払っているかを意識しましょう。
言葉を再定義しましょう。
感想
対照的なAさんとBさん
私は身近に対照的な2人の人がいます。
どちらも豊富な知識をもち、一般的に「頭がいい」と言われる人です。
- 相談をしたり意見を言ったりすると正論を言われてやり込められるので、できることなら相談したくないが、威厳に溢れるAさん。
- 相談すると親身な対応をしてくれ、この人に相談して良かったと思えるが、あまり威厳のないBさん。
昔からAさんに相談すると「正しい答え」が帰ってきます。答えのない問題について議論しても、いつも結論は Aさんの意見に落ち着きます(これが”論破”される、ということだと気づいてさえいませんでした)。
反対にBさんは、一緒にいて居心地の良さはありますが、どことなく頼りないと思っていました。
Bさんは私の話をよく聞いてくれて尊重した上で、求めれば適度なアドバイスをしてくれます。
私はどちらかというとAさんのタイプに慣れていたので、Bさんは賢いのだろうがその賢さの正体がわからないような気がしていました。
しかし、この本を読んで、Bさんのような人がこの本で言われるような「頭のいい人」なのだと思いました。
私はこれまで、自分が「上手く話せない」ことに悩んでいたのですが、こんなに近くに模範となる人がいたとは…(ちなみにAさんは父でありBさんは交際相手です)。
上司との会話
病院で下っ端医師として働いていると、
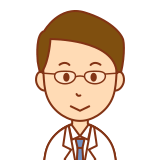
そういえば〇〇さん(患者)ってどうなってるの?退院できそう?
病棟で急に上級医に出くわし、患者さんについて聞かれることが多々あります。
そのような状況下で私が犯すよくある失敗は、
忙しい上級医の時間を無駄にしないようにと思い、慌てて雑な答えをする
↓
上級医は求める回答が得られず、さらに問答を繰り返す
というものです。
その度に「私はどうして瞬時に上司の質問意図を把握し、適切な答えができないのだろうか?」と悩んできました。
この本を読んだ上で言えることは、「考えが足りていないから」です。
上記の例で、上級医の質問と求められている回答を整理すると以下のようになります。
- 上級医はまず患者が退院できるかを気にしているので、退院できるかできないかの結論を言う
- その上で、退院できそうであれば、具体的な退院日を伝えたり、退院までにやらなければならないことを伝える
- 退院できなそうであれば、できない要因となっていることを伝える
私はこれまで、上級医が「そういえば〇〇さん…」と言いかけた段階で、頭の中で〇〇さんの情報を検索し、自分が上級医に何を言うべきかを考えていました。
しかし頭のいい人は「何を言うべきか」を考える前に「上級医は何を知りたいか」を考えるのです。
まとめ
いかがでしたか?
気になった方はぜひ原著を読んでみてください(^^)
話すのが得意な人も苦手な人も、コミュニケーションについて改めて考える一助になると思います!
\ 他にも様々な分野の本を要約しています /